現代社会では、ストレスや不規則な生活習慣により、多くの人が自律神経の乱れを感じています。心身の不調に悩む中で、手軽にセルフケアができる方法として注目を集めているのが「自律神経アプリ」です。特に、テレビ番組『ヒルナンデス!』で紹介されたことで、その存在を知った方も多いのではないでしょうか。「Upmind(アップマインド)」を中心に、自律神経ケアアプリの選び方や、日常生活で取り入れたい習慣について、詳しく解説していきます。
ヒルナンデスで話題沸騰!自律神経ケアアプリ「Upmind」とは?
2025年8月20日、日本テレビ系『ヒルナンデス!』の「夏のイライラ解消 健康企画」にて、自律神経の状態をチェックできるアプリとして「Upmind(アップマインド)」が紹介され、大きな注目を集めました。酷暑が続く中で体の不調を感じる人が多い中、このアプリは夏のイライラ解消法の一つとして専門家によって解説されました。
Upmindは、東京大学発のベンチャー企業が開発したマインドフルネスアプリです。心に余白を持つ習慣を実践することを目的としており、心拍変動解析技術を用いて自律神経のバランス状態を計測し、スコアで表示する画期的な機能を備えています。
『ヒルナンデス!』のスタジオでは、出演者が実際にUpmindを使って自律神経の状態を測定しました。南原さんは副交感神経が92と理想的なバランスを示し、村上さんは44で副交感神経優位、MAYAさんは交感神経優位の44という結果が出たことが報告されています。このように、誰でも簡単に自身の自律神経の状態を客観的に把握できる点が、多くの視聴者の関心を集めました。
Upmindの画期的な機能:あなたの自律神経を見える化
Upmindの最大の特徴は、スマートフォン一つで手軽に自律神経の状態を測定し、見える化できる点にあります。この機能は、日々の心身のコンディションを把握し、適切なケアを行うための第一歩となります。
スマホカメラで簡単測定:心拍変動解析技術
Upmindでは、スマートフォンのカメラに指を30秒間当てるだけで、心拍のゆらぎ(変動)を計測します。この心拍変動解析技術は、自律神経の交感神経と副交感神経のバランスが取れているかを判断し、0から100のスコアで状態を表示します。これにより、目には見えない自律神経の状態を客観的な数値として把握することが可能になります。例えば、スコアが低い場合は副交感神経の働きが低下している可能性があり、リラックスが必要なサインと捉えることができます。
この手軽な測定方法は、忙しい現代人でも日常生活に無理なく取り入れられるよう設計されており、自分の体調変化に気づくきっかけを与えてくれます。
測定結果に基づくパーソナルなアドバイス
自律神経の測定結果に基づいて、Upmindはユーザー一人ひとりに合ったおすすめの過ごし方や改善アクションを提案してくれます。約50種類の習慣の中から、その日の自律神経の状態に最適なアドバイスが提示されるため、何をすれば良いか迷うことなく、効果的なセルフケアに取り組むことができます。
例えば、疲労感が強い日にはリラックス効果のある瞑想を、集中力が必要な日にはマインドフルネスの呼吸法を提案するなど、その時の状態に合わせたきめ細やかなサポートが期待できます。これにより、単に自律神経の状態を知るだけでなく、具体的な改善行動へとつなげることが可能になります。
心と体を整える豊富なコンテンツ
Upmindは、自律神経の測定だけでなく、心と体を総合的にケアするための豊富なマインドフルネスコンテンツを提供しています。専門家が監修したプログラムにより、質の高いセルフケアを自宅で手軽に実践できます。
専門家監修の瞑想プログラム
Upmindには、一般社団法人マインドフルネス瞑想協会代表理事の吉田昌生氏が監修した、多岐にわたる瞑想プログラムが用意されています。瞑想は、心を落ち着かせ、ストレスを軽減し、自律神経のバランスを整えるのに非常に効果的とされています。
忙しい現代人のために、短いものでは2分から始められる「クイック整え」のようなプログラムも充実しており、仕事の合間や移動中など、わずかな時間でも手軽にマインドフルネスを実践できます。継続することで、心の平穏を取り戻し、日々のストレスに負けない心身を育むサポートをしてくれます。
ヨガ・ストレッチで身体からアプローチ
心のケアだけでなく、身体からのアプローチも重要です。Upmindでは、ヨガ講師の梅澤友里香氏監修の下、ストレッチやヨガのガイド動画も提供されています。適度な運動は、自律神経のバランスを整え、血行促進やリラックス効果をもたらします。
肩こりや腰痛の解消を目的とした2分間のプログラムなど、こちらも短時間で取り組めるメニューが豊富に用意されているため、デスクワークの休憩中などにも気軽に体を動かす習慣を取り入れることができます。
質の高い睡眠をサポートする「熟睡」機能
自律神経の乱れは、睡眠の質の低下に直結することが少なくありません。Upmindは、質の高い睡眠をサポートするための「熟睡」機能も充実させています。入眠を促すための心地よい音楽や、「スリープストーリー」と呼ばれる読み聞かせコンテンツが提供されており、特に吉田昌生さんのナレーションは癒されると評判です。
寝る前のリラックスタイムにこれらのコンテンツを利用することで、心身ともに落ち着き、スムーズな入眠と深い眠りをサポートします。十分な睡眠は、自律神経を整え、日中のパフォーマンスを向上させる上で不可欠です。
Upmindが選ばれる理由:科学的根拠と実績
数ある自律神経ケアアプリの中でも、Upmindが多くのユーザーに選ばれ、高い評価を得ている背景には、その科学的な根拠と確かな実績があります。
東京大学との共同研究による科学的裏付け
Upmindは、東京大学大学院(滝沢龍研究室)と共同研究を行い、マインドフルネスの効果について科学的な検証を進めています。臨床精神医学・臨床心理学・メンタルヘルスの専門家である滝沢龍准教授の監修のもと、メンタルヘルス不調の予防・回復効果の向上に関する有用性検証に取り組んでおり、その開発には専門的な知見が反映されています。
このような科学的な裏付けがあることで、ユーザーは安心してアプリを利用し、その効果を信頼することができます。Upmindは、単なるリラックスアプリではなく、心身の健康を科学的にサポートするヘルスケアサービスとして評価されています。
グッドデザイン賞2023受賞の優れたデザインと機能性
Upmindは、その優れたデザインと機能性が高く評価され、2023年にはグッドデザイン賞を受賞しています。落ち着きのあるUI/UXは、ユーザーがストレスなくアプリを利用し、マインドフルネスに集中できる環境を提供します。
デザイン性の高さは、アプリの継続利用にも繋がりやすく、日々のセルフケアを習慣化する上で重要な要素となります。多くのユーザーに支持されている理由の一つに、この使いやすさとデザインの美しさがあると言えるでしょう。
App Store総合ランキング1位獲得と150万ダウンロード突破の実績
2025年8月20日には、UpmindがApp Storeにて全カテゴリの総合ランキングで1位を獲得したことが発表されました。この快挙は、世界的に話題の生成AIサービス「ChatGPT」を抑えての達成であり、マインドフルネスアプリとしては初めてのことです。
さらに、累計ダウンロード数は150万を超え、国内最大のマインドフルネスアプリとしての地位を確立しています。これらの実績は、Upmindが多くの人々に支持され、その効果が広く認められている証拠と言えるでしょう。
Upmindの利用方法と料金プラン
Upmindは、手軽に始められる無料版と、より充実した機能を利用できる有料版があります。ご自身のニーズに合わせて選択することが可能です。
無料版でできること
Upmindの無料版では、自律神経の測定機能を利用できます。スマートフォンのカメラに指を当てるだけで、現在の自律神経のバランスをスコアで確認することが可能です。これにより、自身の心身の状態を客観的に把握し、日々のコンディションを意識するきっかけを得ることができます。
まずは無料で自律神経の測定を試してみて、アプリの使いやすさや測定結果の傾向を確認することをおすすめします。
有料版で利用できる機能と料金
Upmindの有料版(サブスクリプションプラン)では、無料版の測定機能に加えて、以下の豊富なコンテンツが利用できます。
- 専門家監修の瞑想プログラム
- ヨガやストレッチのガイド動画
- 質の高い睡眠をサポートする入眠音楽やスリープストーリー
- 自律神経のバランス改善に向けたパーソナルなアドバイス
- 計測結果の推移や統計情報を確認できるデータ機能
- 自律神経に関する医学的な情報が閲覧できる学習機能
これらの有料コンテンツを利用することで、より深く、継続的に自律神経ケアに取り組むことができます。料金については、アプリ内で確認できますが、一般的には月額または年額のサブスクリプション形式が採用されています。
無料トライアルと自動課金の注意点
有料プランには、多くの場合、無料トライアル期間が設けられています。この期間中にアプリの全機能を試すことができますが、無料トライアル期間が終了する前に解約手続きを行わないと、自動的に有料プランへ移行し課金が開始される点には注意が必要です。利用規約をよく確認し、ご自身の利用状況に合わせて管理しましょう。
Upmindの公式URL
Upmindのダウンロードは、以下の公式ストアから行えます。
- App Store: Upmind – 自律神経・瞑想・マインドフルネス・睡眠
- Google Play: Upmind – 自律神経・瞑想・マインドフルネス・睡眠
また、Upmindの公式サイトはこちらです: Upmind(アップマインド)
注意事項:Upmindはヘルスケアアプリであり、医療機器プログラムではありません。疾病の治療、診断、予防を目的としたものではなく、医療機関の診断の代替になるものではないため、体調不良が続く場合は必ず専門の医療機関を受診してください。
自律神経を整えるアプリを選ぶ際のポイント
自律神経ケアアプリはUpmind以外にも多数存在します。ご自身に合ったアプリを選ぶためには、いくつかのポイントを押さえておくことが大切です。
信頼性・監修者の有無
アプリを選ぶ上で最も重要なのは、その信頼性です。医療従事者や専門家が監修しているアプリは、科学的な根拠に基づいたプログラムを提供している可能性が高く、安心して利用できます。Upmindのように東京大学との共同研究を行っているアプリは、その信頼性が高いと言えるでしょう。また、CARTEのように順天堂大学医学部の教授が監修しているアプリもあります。
機能の網羅性(測定、コンテンツ、記録)
自律神経ケアには、現在の状態を把握する「測定」、状態を改善するための「コンテンツ」、そして変化を振り返る「記録」の3つの要素が重要です。これらの機能が網羅されているアプリを選ぶことで、より効果的なセルフケアが期待できます。Upmindはこれらの機能をバランス良く提供しています。
使いやすさ・継続性
どんなに良い機能があっても、使いにくければ継続は困難です。直感的でわかりやすいUI/UX、短時間で手軽に利用できるコンテンツ、そして継続を促す工夫(例えば、AIによる褒め機能など)が施されているアプリを選ぶと良いでしょう。
無料版の有無
いきなり有料アプリに課金するのは抵抗があるかもしれません。まずは無料版で基本的な機能を試したり、無料トライアル期間を利用したりして、ご自身に合っているかを確認することをおすすめします。UpmindやHabitoneのように、無料版で自律神経測定ができるアプリもあります。
Upmind以外の自律神経ケアアプリ
Upmind以外にも、自律神経のケアに役立つアプリはいくつか存在します。ここでは、代表的なものをいくつかご紹介します。
Habitone(ハビトーン):習慣化で心身を整える
Habitone(ハビトーン)は、「習慣で毎日を整える」ことをコンセプトにしたセルフコンディショニングアプリです。以前は「ストレススキャン」という名称で300万ダウンロードを記録したストレスチェックアプリがリニューアルしたものです。
スマートフォンのカメラで心拍変動(HRV)を測定し、自律神経バランスのゆらぎを見える化します。日々の体調や睡眠を記録できるほか、記録から可視化された不調に対して、専門家監修のセルフケア提案を日々の習慣に組み込むことで、心身の状態を整え「いい日」を増やすサポートをしてくれます。有料版と無料版があり、利用できる機能が異なります。
公式サイト: Habitone(ハビトーン)|自律神経・習慣で毎日を整える
CARTE(カルテ):小林弘幸教授監修の「インナーパワー」測定
CARTE(カルテ)は、自律神経研究の第一人者である順天堂大学医学部教授の小林弘幸氏が全面監修しているアプリです。スマートフォンのバックカメラに60秒指を置くだけで、自律神経の状態を「新指標 インナーパワー」として1〜100の数値でスコア化します。
測定結果に基づいて、小林弘幸教授の「自律神経改善コメント」や、ストレスフリーな「自律神経エクササイズ」が提案され、セルフコントロールをサポートします。自律神経の乱れが、朝起きられない、疲れやすい、肩こり、イライラなどの原因となることに着目し、体の内側からキレイになることを目指します。
アプリと併用したい自律神経を整える生活習慣
自律神経ケアアプリは強力なツールですが、アプリだけに頼るのではなく、日々の生活習慣を見直すことも非常に重要です。アプリと併用することで、より効果的に自律神経のバランスを整えることができます。
規則正しい生活リズム
自律神経は、日中の活動を司る交感神経と、夜間の休息を司る副交感神経がバランスを取りながら働いています。このリズムを整えるためには、毎日同じ時間に起床し、就寝することが大切です。特に、朝日を浴びることは、体内時計をリセットし、セロトニンの分泌を促す効果があると言われています。
バランスの取れた食事
腸と脳は密接に関係しており、「腸脳相関」と呼ばれるメカニズムがあります。腸内環境を整えることは、自律神経のバランスにも良い影響を与えます。発酵食品や食物繊維を豊富に含む食材を積極的に摂り、バランスの取れた食事を心がけましょう。また、カフェインやアルコールの過剰摂取は、自律神経を刺激し、乱れの原因となることがあるため注意が必要です。
適度な運動
無理のない範囲で、ウォーキングや軽いジョギング、ストレッチなどの有酸素運動を習慣にしましょう。運動はストレス解消になり、血行促進やリラックス効果も期待できます。特に、夕方以降に軽い運動を取り入れると、心地よい疲労感で質の良い睡眠につながることもあります。
入浴やアロマなどリラックス法
ストレスを感じやすい現代において、意識的にリラックスする時間を作ることは非常に大切です。ぬるめのお湯にゆっくり浸かる入浴、アロマオイルを使った芳香浴、好きな音楽を聴く、読書をするなど、ご自身が心地よいと感じるリラックス法を見つけて、日々の生活に取り入れましょう。Upmindのようなアプリの瞑想コンテンツも、手軽なリラックス法として活用できます。
専門家への相談の重要性
自律神経の乱れによる不調が長く続く場合や、日常生活に支障をきたすほど症状が重い場合は、アプリだけに頼らず、必ず専門の医療機関を受診してください。心療内科や精神科、自律神経専門のクリニックなど、適切な診断と治療を受けることが大切です。アプリはあくまでセルフケアの補助ツールであり、医療行為の代替にはなりません。
まとめ
現代社会において、自律神経の乱れは多くの人が抱える課題です。そんな中で、手軽に自身の状態を把握し、ケアできる自律神経アプリは、心身の健康を保つための強力な味方となります。特に、テレビ番組『ヒルナンデス!』で紹介された「Upmind」は、その科学的根拠と豊富な機能、そして多くの実績から、今最も注目されているアプリの一つと言えるでしょう。
自律神経アプリ「Upmind」で心と体のバランスを整える
Upmindは、スマートフォンのカメラで簡単に自律神経の状態を測定できるだけでなく、東京大学との共同研究に裏打ちされた信頼性の高いマインドフルネスコンテンツを提供しています。専門家監修の瞑想やヨガ、質の高い睡眠をサポートする機能など、心と体を総合的にケアするためのプログラムが充実しており、2023年にはグッドデザイン賞も受賞、App Store総合ランキング1位を獲得するなど、その効果と人気は確かなものです。無料版で自律神経測定を体験し、必要に応じて有料版の豊富なコンテンツを活用することで、日々のストレスを軽減し、心にゆとりを持った生活を送るための一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。アプリと並行して、規則正しい生活、バランスの取れた食事、適度な運動、リラックスタイムの確保といった基本的な生活習慣を見直すことも忘れずに行い、もし不調が続くようであれば、専門の医療機関への相談も視野に入れることが大切です。Upmindを賢く利用し、あなた自身の心と体の健康を育んでいきましょう。

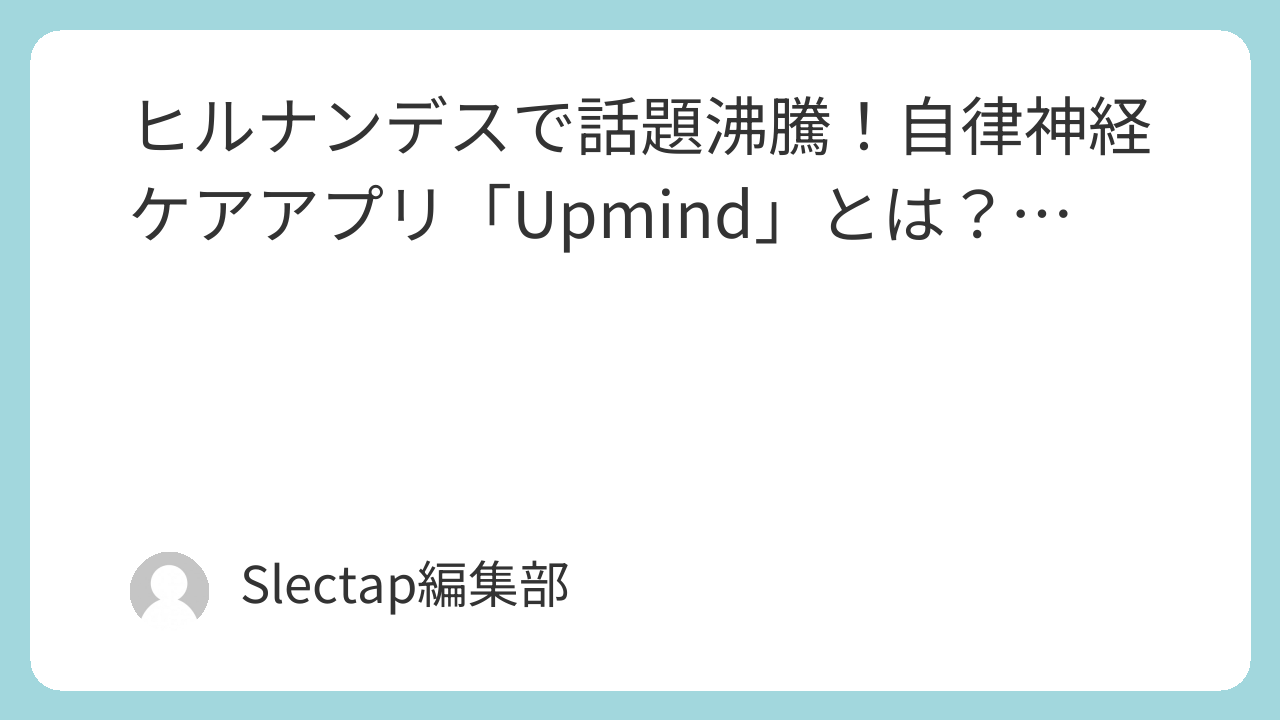
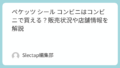
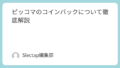
コメント